不動産投資で節税できる?節税の仕組みや失敗事例、注意点を解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産
不動産投資で節税できる?節税の仕組みや失敗事例、注意点を解説!
2025-05-09

不動産投資では、減価償却費の活用や損益通算による所得税・住民税の減税、貸付建付地の評価適用による相続税の減税などが期待できます。
ただし、不動産投資での節税は仕組みが複雑で、ベテランの賃貸オーナーでも節税方法の詳細について知らない方は少なくありません。
そこで、本記事では、不動産投資で節税できる税制上の仕組みや、節税シミュレーションについて解説します。不動産投資で節税効果を得やすい物件・得にくい物件や、節税目的の不動産投資でよくある失敗事例についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
不動産投資は方法次第で、1つの所得にかかる税金を減らす効果が期待できます。節税できる可能性のある税金は次のとおりです。
1. 所得税
所得税は、個人の所得に対して課される税金です。1年間のすべての収入金額から、必要経費や控除所得額といった所得控除を差し引いた課税所得に累進課税制度を適用し税額を計算します。
2. 住民税
住民税は、その地域に住む人たちが、地域社会の公共サービスを維持するために負担する税金です。企業などが負担する「法人住民税」とその市区町村・都道府県に住所を有する個人が負担する「個人住民税」に分けられます。
3. 贈与税
贈与税は個人から贈与の形式で財産を譲り受けたときにかかる税金です。超過累進課税という課税方式が採用されており、贈与財産の価額が大きければ大きいほど、税率が高くなります。
4. 相続税
相続税は、亡くなった親や配偶者などから財産を引き継いだときに発生する税金です。現金や株・債券といった金融資産だけでなく、土地・建物といった実物資産も課税対象となります。
5. 法人税
法人税は、法人の企業活動により得られた所得に対して課される税金です。個人名義ではなく、株式会社や合同会社といった法人として投資した場合は、通年の所得に対して、法人税が発生します。

不動産投資で節税できるのは、次の4つの税制上の仕組みが影響しています。
- 減価償却を活用して課税所得額を抑えられる
- 損益通算で赤字を他の所得と相殺できる
- 相続時は不動産評価額が低くなる
- 法人化で税率を低くできる
これらの仕組みは不動産投資による節税を理解するうえで重要です。ぜひ参考にしてください。
減価償却を活用して課税所得額を抑えられる
不動産投資では、減価償却を活用して課税所得税を抑えることが可能です。
減価償却とは、経年劣化を伴う建物や機械、自動車といった減価償却資産を、法定耐用年数(法律で定められた、建物の価値がなくなるまでの年数)分だけ分割して経費に計上すること。減価償却を活用すると、減価償却資産の購入費を購入した年の経費として全額計上するのではなく、法定耐用年数に応じて分割計上していくことが可能です。
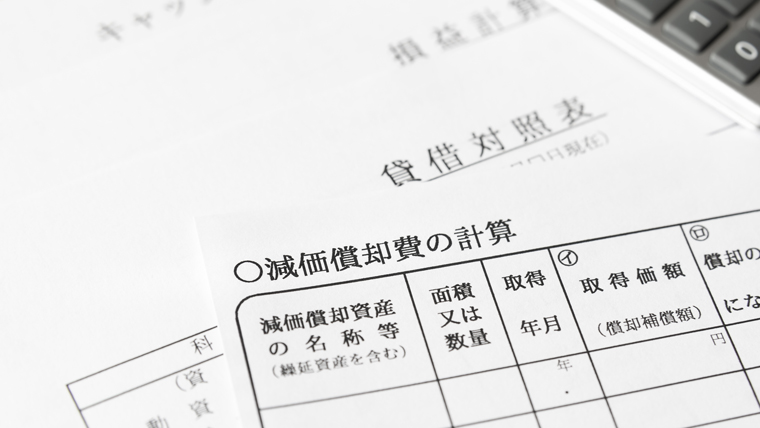
法定耐用年数に応じた経費の分割計上により、不動産購入時から法定耐用年数が経過するまでの間、課税所得額を少なく申告できるため、所得税や住民税を減税できます。
ただし、土地は、時間の経過によって価値が減少しないため、減価償却の対象外です。
損益通算で赤字を他の所得と相殺できる
不動産投資では、不動産所得に生じた損失を、給与所得や事業所得といった他の所得と相殺することが可能です。こうした税制上の仕組みを「損益通算」と呼びます。
たとえば、給与所得で800万円の収入があるサラリーマンが不動産投資で200万円の赤字を出した場合、損益通算によって給与所得を600万円に減額可能です。給与所得が減額されれば、課税所得額も少なくなるため、住民税や所得税の減税につながります。
なお、青色申告で不動産所得に生じた損失と他の所得と損益通算しても赤字が残る場合は、損失額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
相続時は不動産評価額が低くなる
贈与税や相続税の算出に用いる不動産の評価額(相続税評価額)は、実際に売買される時価(地価公示価格)のおよそ8割で評価されます。
たとえば、5,000万円の現金を相続する場合、相続税評価額は5,000万円すべてが対象になるのに対し、時価が5,000万円の不動産を相続する場合は相続税評価額が4,000万円になります。減価償却費や損益通算と同じような原理で、相続税評価額が少なくなれば、課税対象額も少なくなるため、結果として相続税を抑えられるというわけです。
さらに、贈与や相続の対象となる不動産が収益物件の場合、土地は「貸家建付地」としての評価が適用されるため、さらに相続税評価額を減額できます。
貸家建付地とは、貸家の敷地として使用されている宅地(アパートやマンションなどの賃貸物件が建っている土地)のこと。貸家建付地の評価が適用される収益物件の土地の相続税評価額は、「賃貸に出している分、所有者の自由にできない」ことを理由に減額してもらえます。計算式は次のとおりです。
貸付建付地の相続税評価額=自用地としての土地価額-(自用地としての土地価額-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
ここでいう「自用地としての土地価額」とは、相続税評価額による評価額のこと。一方、借地権割合と賃貸割合については、地域や物件によって異なりますが、借地権割合については全国一律で30%となっています。
仮に5,000万円の収益物件の土地価額に借地権60%、借家権割合30%、賃貸割合90%という条件を当てはめた場合、相続税評価額は2段階の計算を経て次のように導き出されます。
収益物件の土地の相続税評価額(路線価):5,000万円(時価)×80%=4,000万円
貸付建付地の相続税評価額:4,000万円-(4,000万円×60%×30%×90%)=3,352万円
このように、不動産が収益物件の場合、貸付建付地の評価の適用により、土地の相続税評価額が小さくなるのです。また、収益物件の建物の相続税評価額も、土地と同様に減額できます。
収益物件の建物の相続税評価額は次のとおりです。
収益物件の建物の相続税評価額=固定資産税評価額-(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)
以上のように、不動産はそもそも相続税評価額が低い傾向にありますが、収益物件として所有すれば、相続税評価額をさらに減額可能です。これが、「不動産投資は相続税の節税対策に有効」といわれるゆえんです。
不動産投資を通じた相続税の節税については、タワマン節税のルール改正に関する記事でも解説しているため、ご参考にしてください。
タワマン節税のルール改正とは?改正された背景や改正による影響も解説!
法人化で税率を低くできる
個人の不動産所得には所得税の税率が適用されますが、法人化すれば課税所得額に法人税率が適用されるため、節税できる可能性があります。法人税率は一定の所得額を超えると個人の所得税率より低くなるためです。
法人税率が所得税率より低くなるのは、年間の課税所得額が900万円を超える場合です。課税所得額が900万円を超える場合は、「所得税率(33%)>法人税率(23.2%)」となるため、法人化による節税効果を得られるようになります。
結論からいうと、節税目的の不動産投資が向いている人は課税所得額が900万円を超える人です。
ここからは、その理由について、詳細に説明するので、ぜひ参考にしてください。
節税目的の不動産投資が向いている人
節税目的の不動産投資が向いている人は、課税所得額が900万円(年収1,200万円)以上の所得者です。課税所得額が900万円を超えると所得税の税率が33%となり、5年超の長期保有の場合、譲渡所得税率(20%)との差が13%と大きくなり、不動産譲渡時の減税額が大きくなります。
この減税メカニズムを説明するため、収益物件を6年所有する賃貸オーナーが6年目の確定申告で、不動産収入から100万円分を減価償却費として所得控除したとします。すると、賃貸オーナーは、100万円の減価償却に対して33万円の節税効果を獲得します。
一方、減価償却により税務上の取得価額が100万円引き下げられ、将来の譲渡所得が100万円分増加します。この譲渡所得の増加によって、その賃貸オーナーに対して20万円の譲渡所得税が潜在的に課されます。
潜在的に課された譲渡所得税はすぐさま発生するわけではありません。あくまでも高税率での控除と低税率での課税という税率の差から生まれる効果であり、最終的には譲渡時点で13万円分の節税が確定するというわけです。
節税目的の不動産投資が向いていない人
節税目的の不動産投資が向いていない人は譲渡所得額が900万円(年収1,200万円)未満の方です。課税所得額が900万円未満の場合は所得税の税率と譲渡所得税率の差が小さく、不動産譲渡時の減税額も小さくなります。
しかし、譲渡所得額が900万円未満でも、不動産投資での節税効果が得られないというわけではありません。損益通算による給与所得の圧縮や、青色申告による課税所得額の減額といった方法を採用すれば、不動産投資での節税効果が期待できるでしょう。
不動産投資で節税効果を十分に得るためには、適切な物件を選ぶことが大切です。
ここからは、不動産投資で節税効果を得やすい物件・得にくい物件について解説します。
不動産投資で節税効果を得やすい物件
不動産投資で節税効果を得やすいのは、中古マンションと木造住宅です。
まず中古マンションが節税効果を得やすいのは、中古物件の耐用年数を求める計算式が「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」になっていることに起因します。この計算式により、同じ建築物でも、中古物件は耐用年数が延び、より長期に減価償却費を計上できるのです。
たとえば、築30年が経過した中古の鉄筋コンクリート(RC)造のマンションを購入したと仮定しましょう。RC造の法定耐用年数は47年のため、このマンションの耐用年数は、「(47-30)+ 30×20%」=23年となります。

RC造のマンションを新築で購入した場合、築30年後に減価償却費できる残りの期間は17年です。しかし、同じ物件を築30年後に中古として購入すれば減価償却できる期間は従来より6年長い23年となります。つまり、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造やRC造の中古マンションを購入すると、減価償却を計上できる期間が長くなり、節税できる期間も長くなるというわけです。
他方、木造または合成樹脂造の法定耐用年数は22年です。他の構造と比べて短いため、同じ価格の不動産を取得した場合は、法定耐用年数が短い木造住宅の方が1年あたりの減価償却費が増えるため、節税効果は大きくなります。
不動産投資で節税効果を得にくい物件
不動産投資で節税効果を得にくい物件は新築の区分マンションです。
SRC造あるいはRC造の新築区分マンションは47年の法定耐用年数に呼応する形で減価償却期間が長く、1年間に計上できる減価償却費が少額になります。減価償却費が少額になれば、課税所得額が増えるため、節税効果も小さくなります。
たとえば、年収1,000万円のサラリーマンが投資目的の新築区分マンションを1億円で購入した場合、毎年の減価償却費は約213万円です。この場合、サラリーマンの手取りが780万円だとしても減価償却費によって会計上の赤字を作り出せません。
このように、減価償却費の計算上、新築の区分マンションは節税に向いていないといえるでしょう。

不動産投資における節税シミュレーションは、次のとおりです。
- 不動産投資にかかる必要経費を確認する
- 不動産収入を計算する
- 不動産所得を計算する
実際の節税フローはもっと複雑ですが、これらの流れを押さえると、不動産投資における節税がイメージしやすくなります。ぜひ参考にしてください。
不動産投資にかかる必要経費を確認する
まずは不動産投資にかかる必要経費を確認します。主な必要経費の項目については、次のとおりです。
- 貸倒金
- 地代家賃
- 借入金利子
- 租税公課
- 修繕費
- 管理費
- 減価償却費
- 人件費
これらの項目のうち、減価償却費については、毎年同額の減価償却費を計上する定額法か、減価償却費が減価償却資産を取得した初めの年が一番多く、年とともに減少する定率法によって求めます。
不動産収入を計算する
続いて、不動産投資による収入を計算します。不動産収入には、賃貸料だけでなく、次のような項目も含まれます。
- 敷金・礼金
- 保証金
- 更新料
- 譲渡承諾料(名義書換料)
- 共益費・管理費
- 駐車場代
不動産所得を計算する
不動産所得は次の計算式で算出します。
不動産所得=不動産総収入金額-必要経費
必要経費が不動産総収入金額を上回って赤字がでた場合には、給与所得や年金といった他の所得と損益通算(相殺)しましょう。
不動産所得が計算できたら、税務署に申告書を提出する確定申告を行います。税務署に「不動産所得と納税額を正しく申告した」と認められれば、不動産投資での節税が完了です。

節税目的の不動産投資でよくある失敗事例には次の3つがあります。
- 長期保有により売却のタイミングを逃す
- 不動産売却を急ぎ過ぎたことで税負担が増える
- 理想どおりの収入が得られない
いずれも節税目的の不動産投資で起こりうる頻出例ですので、ぜひ参考にしてください。
長期保有により売却のタイミングを逃す
長期にわたって収益物件を所有していると、減価償却費を会計帳簿に計上できない時期が訪れます。減価償却費を計上できるのは、耐用年数省令に基づき、構造物の耐用年数以内と決められているためです。
耐用年数を超えた収益物件は減価償却費を計上できません。結果、不動産所得が黒字になり、かえって税負担が増えるケースもあります。
さらに、築年数が経過した収益物件は修繕費の増加や資産価値の低下が危惧されます。そのため、収益物件は耐用年数の範囲内で売却するのがおすすめです。
売却を急ぎ過ぎたことで税負担が増える
収益物件は売却が早すぎると税負担が増える恐れがあります。売却にかかる譲渡所得の税率は所有期間が5年を超えるかどうかによって異なるためです。
実際、所有期間が5年以下の短期譲渡所得は税率が39.63%(所得税30.63%、住民税9%)、所有期間が5年超の長期譲渡所得は税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
このように、譲渡所得に対しては所有期間が5年を超えるまで高い税率が適用されます。こうした税制上の仕組みを踏まえ、収益物件は売却を急ぎ過ぎず、長期譲渡所得の税率が適用される所有6年目まで保有するのが賢明です。
理想どおりの収入が得られない
不動産投資では、空室期間の長期化や賃料下落により、理想どおりの収入が得られない場合があります。
十分な収益を確保できなければ、節税目的の不動産投資をしている場合ではありません。新聞広告やウェブ広告といった不動産広告の展開や、家賃の見直しなどを通じ、収益の回復を図る必要があるでしょう。
このように、不動産投資では、期待していた収入を得られないケースも多々あるため、予期せぬトラブルに備えて、余裕を持った資金計画を立てることも大切です。

節税対策で不動産投資に取り組む際の注意点は、次の3つです。
- 節税効果ばかりに目を向けない
- 節税するために確定申告を必ずする
- 定期的に節税効果をシミュレーションする
いずれも不動産経営に取り組む際の基本事項ですが、取り組むことで着実な節税効果を得られます。ぜひ参考にしてください。
節税効果ばかりに目を向けない
節税対策で不動産投資に取り組む際は節税効果ばかりに目を向けないことが大切です。不動産投資は収益確保と将来的な資産形成が主目的であるためです。
したがって、収益物件を購入して運用・管理する際は、まず物件の収益性や将来性を重視しましょう。節税はあくまでも不動産投資に付随したメリットとして捉えるのが無難です。
節税するために確定申告を必ずする
不動産投資で得た収入を節税するためには、必ず確定申告をしなければなりません。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。不動産収入を最大限節税するためには、青色申告で確定申告をするとよいでしょう。青色申告には、白色申告にはない特典があるためです。
このうち、最も恩恵が大きい特典が、青色申告特別控除です。この控除では、事業的規模であり、貸借対照表を作成している場合に最大で65万円控除してもらえます。
このほか、青色申告には純損失が繰越控除できるといったメリットもあるため、青色申告を使わない手はないといえるでしょう。
定期的に節税効果をシミュレーションする
節税目的で不動産投資に取り組む際は、税理士や不動産鑑定士といった専門家を交えて定期的に節税効果をシミュレーションしましょう。不動産投資の節税効果は物件の状況や税制改正、金利環境に応じて変化するためです。
これを踏まえ、節税効果の明確化を目的としたシミュレーションは、新しい税制が始まる年度始めに作成するとよいでしょう。
不動産投資による節税効果は、減価償却費の帳簿への計上や相続税評価額の適用など、複数の方法を組み合わせることで最大化します。
特に所得税率が33%より大きくなる課税所得900万円(年収1,200万円)以上の方は、大きな節税効果を得られるでしょう。
とはいえ、不動産投資で重要なのは収益確保と将来的な資産形成です。あくまでも節税は付随的なメリットとして捉え、計画的に不動産投資に取り組んでください。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30~18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.


