【不動産投資初心者必見】貸借対照表の読み方・作り方を理解しよう | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産
【不動産投資初心者必見】貸借対照表の読み方・作り方を理解しよう
2025-09-19
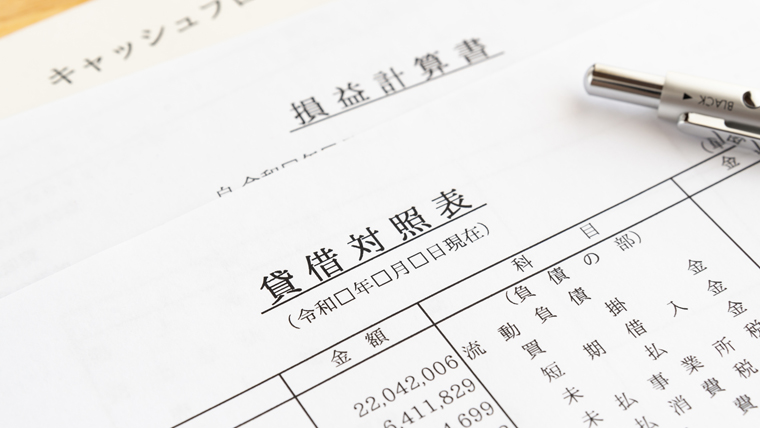
会社勤めの傍ら副業として取り組んでいる方には実感しづらいかもしれませんが、不動産投資もある意味立派な事業の一種です。そのため、定期的に「自分の事業における資産の状態」や「事業で利益が上がっているか」を振り返る必要があります。そこで重要になるのが財務諸表の作成と検証です。
この記事では、不動産投資における重要な財務諸表の一種・貸借対照表について知っておくべきことをまとめました。
貸借対照表とは、作成時点における企業もしくは事業主の財政状態を表す財務諸表の一種です。英語では「Balance sheet(バランスシート)」と呼ばれ、「B/S」という略称が用いられることもあります。
一般的な貸借対照表の例は、以下のとおりです。
| (資産の部) | (負債の部) |
|---|---|
| 流動資産 | 流動負債 |
| 固定資産 | 固定負債 |
| 有形固定資産 | 合計 |
| 投資その他の資産 | (資本(純資産)の部) |
| 繰延資産 | 剰余金 |
| 資産合計 | 資本(純資産)合計 |
| 負債・資本合計 |
このように、1つの表にまとまっている形式を「勘定式」というのに対し、上から順に資産、負債、資本の順に並べていく形式を「報告式」と言います。
| (資産の部) |
|---|
| 流動資産 |
| 固定資産 |
| 有形固定資産 |
| 投資その他の資産 |
| 繰延資産 |
| 資産合計 |
| (負債の部) |
| 流動負債 |
| 固定負債 |
| 合計 |
| (資本(純資産)の部) |
| 法定準備金 |
| 剰余金 |
| 資本(純資産)合計 |
| 負債・資本合計 |
なお、報告式は古い様式とされているため、現在は勘定式が主流です。勘定式は左右の金額を比べやすいというメリットもあるため、基本的には勘定式を使いましょう。
貸借対照表の右と左は必ず一致する
貸借対照表の大きな特徴として「右と左は必ず一致する」ことが挙げられます。貸借対照表の左(借方)には資産を、右(貸方)には負債および純資産を書きますが、右と左の数値は常に一致する仕組みです。
理由として、資産は自分が調達した資金の運用状況、負債や純資産は資金の調達方法を表していることが挙げられます。つまり、同じものを表と裏の双方から見ているにすぎないため、金額は常に一致すると考えましょう。
既に触れたように、貸借対照表は以下の3つの部から構成されています。
- 資産の部
- 負債の部
- 純資産の部
<貸借対照表の例>※単位:円
| 会社もしくは事業主が持っている資産 | 資産の部 | 負債の部 | 他人資本 | 財産の元になったお金の調達方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 流動負債 | |||||
| 現金預金 | 10,000 | 支払手形 | 10,000 | |||
| 受取手形 | 20,000 | 買掛金 | 10,000 | |||
| 売掛金 | 40,000 | 短期借入金 | 2,000 | |||
| 有価証券 | 10,000 | 未払金 | 10000 | |||
| 商品 | 4,000 | その他 | 20,000 | |||
| その他 | 16,000 | 固定負債 | ||||
| 固定資産 | 長期借入金 | 100,000 | ||||
| 土地 | 50,000 | 社債 | 30,000 | |||
| 建物 | 60,000 | その他 | 4,000 | |||
| 機械装置 | 20,000 | 純資産の部 | 自己資本 | |||
| その他 | 60,000 | 株主資本 | ||||
| 繰延資産 | 資本金 | 100,000 | ||||
| 開業費 | 5,000 | 資本剰余金 | 4,000 | |||
| その他 | 5,000 | 利益剰余金 | 10,000 | |||
| 資産合計 | 300,000 | 負債・ 純資産合計 |
300,000 | |||
まずは基本的な知識として「どこに何が書いてあるのか」を理解しましょう。
資産の部
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 流動負債 | ||
| 現金預金 | 10,000 | 支払手形 | 10,000 |
| 受取手形 | 20,000 | 買掛金 | 10,000 |
| 売掛金 | 40,000 | 短期借入金 | 2,000 |
| 有価証券 | 10,000 | 未払金 | 10000 |
| 商品 | 4,000 | その他 | 20,000 |
| その他 | 16,000 | 固定負債 | |
| 固定資産 | 長期借入金 | 100,000 | |
| 土地 | 50,000 | 社債 | 30,000 |
| 建物 | 60,000 | その他 | 4,000 |
| 機械装置 | 20,000 | 純資産の部 | |
| その他 | 60,000 | 株主資本 | |
| 繰延資産 | 資本金 | 100,000 | |
| 開業費 | 5,000 | 資本剰余金 | 4,000 |
| その他 | 5,000 | 利益剰余金 | 10,000 |
| 資産合計 | 300,000 | 負債・ 純資産合計 |
300,000 |
資産の部には、その会社もしくは事業主が保有する財産が記載されます。ここでいう資産とは、預貯金や不動産のような金銭的な価値を持つ財産に限りません。将来的に会社もしくは事業主に収益をもたらす可能性があるものも資産として扱います。
なお、貸借対照表上においては、流動性が高い資産から順に記載するのが一般的なルールです。つまり、現金化しやすい、売買しやすいものから順に書くと考えましょう。
貸借対照表上では、資産をさらに以下の3つに分類して書きます。
流動資産
流動資産とは、企業もしくは事業主が保有する資産のうち、1年以内に現金化できる可能性が高い資産を指します。具体例は以下のとおりです。
- 現金
- 預金
- 株式などの有価証券
- 売掛金
- 短期貸付金
- 棚卸資産
固定資産
固定資産とは、企業もしくは事業主が保有する資産のうち、現金化するのに1年以上かかるものや、そもそも長期にわたって保有することを予定しているものを指します。
基本的にすぐに現金化できない、もしくはそもそも現金化するつもりがないものが入ると考えましょう。具体例は以下の通りです。
- 土地
- 建物
- 機械
- 車
- ソフトウェア
- 長期貸付金
- 投資有価証券
また、物理的な形の有無や目的という観点から、さらに以下の3つに分類できます。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 有形固定資産 | (投資用以外の)建物や土地、車、機械など |
| 無形固定資産 | 法律上の権利、ソフトウェア、長期貸付金など |
| 投資その他の資産 | (投資用の)建物や土地、株式、投資信託など |
不動産投資のために保有するマンション、アパートなどは「投資その他の資産」に入ります。
繰延資産
繰延資産とは、すでに発生し、支払いも済んだ費用の一部を資産として計上し、年度をまたいで費用化していくものを指します。支出したサービスや品物の効果が1年以上に及ぶことから、会計上、資産として処理しているのが大きな特徴です。
具体的に繰延資産として計上できるものは以下のとおりです。
| 種類 | 内容 | 償却年数 | 損益計算書のどこに計上するか |
|---|---|---|---|
| 創立費 | 会社の設立登記を行うまでにかかった費用 | 5年以内 | 営業外費用 |
| 開業費 | 設立登記が済んでから営業を開始する までにかかった費用 |
5年以内 | 営業外費用もしくは販売費及び一般管理費 |
| 開発費 | 新しい技術や資源の開発、マーケットの開拓に要した費用 | 5年以内 | 売上原価または販売費及び一般管理費 |
| 株式交付費 | 会社を設立した後、新株式を発行した際に要した費用 | 営業外費用 | 3年以内 |
| 社債発行費 | 社債を発行するのにかかった費用 | 社債の償還期限内 | 営業外費用 |
補足として、繰延資産の種類が極めて限られている理由についても触れておきましょう。繰延資産はあくまで費用を長期にわたって振り分けていくために資産として計上したものに過ぎず、有形固定資産や無形固定資産のように換金性はありません。財務上はむやみに計上することが好ましくないため、計上できる項目は極めて限定されています。
負債の部
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 流動負債 | ||
| 現金預金 | 10,000 | 支払手形 | 10,000 |
| 受取手形 | 20,000 | 買掛金 | 10,000 |
| 売掛金 | 40,000 | 短期借入金 | 2,000 |
| 有価証券 | 10,000 | 未払金 | 10000 |
| 商品 | 4,000 | その他 | 20,000 |
| その他 | 16,000 | 固定負債 | |
| 固定資産 | 長期借入金 | 100,000 | |
| 土地 | 50,000 | 社債 | 30,000 |
| 建物 | 60,000 | その他 | 4,000 |
| 機械装置 | 20,000 | 純資産の部 | |
| その他 | 60,000 | 株主資本 | |
| 繰延資産 | 資本金 | 100,000 | |
| 開業費 | 5,000 | 資本剰余金 | 4,000 |
| その他 | 5,000 | 利益剰余金 | 10,000 |
| 資産合計 | 300,000 | 負債・ 純資産合計 |
300,000 |
負債とは、企業や事業主に生じた返済・支払いの義務を負うマイナスの財産を指します。簡単にいうと「支払い、返済の義務があるもの」と考えましょう。
負債も資産と同様「1年以内に返済・支払いの義務が生じるか」をもとに、流動負債と固定負債のいずれかに分類されます。
流動負債
1年以内に返済・支払いの義務が生じる負債のことを流動負債と言います。具体例は以下のとおりです。
- 買掛金
- 未払金
- 前受金、前受収益
- 短期借入金
- 賞与引当金
固定負債
固定負債とは、1年を超えて返済・支払いの義務が生じる負債を指します。具体例は以下のとおりです。
- 社債
- 長期借入金
- 退職給付引当金
ここで「退職給付引当金」について説明しておきます。これは、従業員に対し退職金を出している場合、将来問題なく支払いができるよう現在までに発生している分を見積もり計上するための勘定科目です。法人・個人事業主問わず、自分だけで不動産投資をやっているならあまり関係ないかもしれませんが、教養として知っておくとよいでしょう。
純資産の部
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 流動資産 | 流動負債 | ||
| 現金預金 | 10,000 | 支払手形 | 10,000 |
| 受取手形 | 20,000 | 買掛金 | 10,000 |
| 売掛金 | 40,000 | 短期借入金 | 2,000 |
| 有価証券 | 10,000 | 未払金 | 10000 |
| 商品 | 4,000 | その他 | 20,000 |
| その他 | 16,000 | 固定負債 | |
| 固定資産 | 長期借入金 | 100,000 | |
| 土地 | 50,000 | 社債 | 30,000 |
| 建物 | 60,000 | その他 | 4,000 |
| 機械装置 | 20,000 | 純資産の部 | |
|---|---|---|---|
| その他 | 60,000 | 株主資本 | |
| 繰延資産 | 資本金 | 100,000 | |
| 開業費 | 5,000 | 資本剰余金 | 4,000 |
| その他 | 5,000 | 利益剰余金 | 10,000 |
| 資産合計 | 300,000 | 負債・ 純資産合計 |
300,000 |
純資産とは、資本から負債を差し引いたもので、自己資本と呼ばれることもあります。主な内訳は以下のとおりです。
- 株主資本
- 評価換算差益等
- 新株予約権
このうち、株主資本はさらに次の3つに細かく分けられます。
| 資本金 | 株主が出資したお金のうち、特に最初に出資した部分 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 株主が出資したお金のうち、資本金を元手にして増やした利益の部分 |
| 資本剰余金 | 株主が出資したお金のうち、資本金に組み入れていないものや、資本取引により生じた剰余金など |
なお、資本金はあくまで法人=会社を作る際に必要となるものであり、個人事業主の場合は必要ありません。ただし、同様の意味合いを持つまとまったお金として元入金を準備することはあります。元入金の金額に制限はないため、ゼロ円でも事業を始めることは可能です。
貸借対照表の数値は、不動産投資を含む事業を展開する際に非常に有用なデータです。ここでは、貸借対照表を活用し、自身が行っている不動産投資について、事業として大きな問題を抱えていないか分析する方法を紹介します。どれも簡単にできるものばかりなので、ぜひ試してください。
資金繰りが大丈夫か知りたい
まず、資金繰りに大きな問題が生じていないか知る簡単な手段として、流動資産と流動負債に着目する方法を解説します。
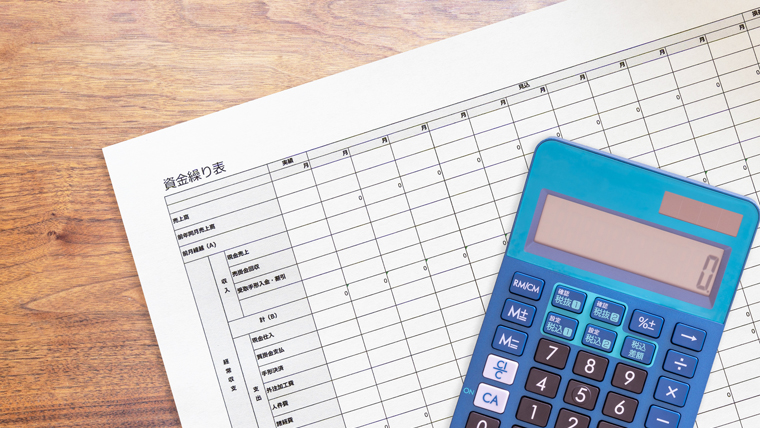
流動資産とは1年以内の現金化が見込まれる資産、流動負債は1年以内の返済が求められる負債です。そのため「流動資産>流動負債」になっていれば、少なくとも向こう1年程度は資金繰りに大きな問題はないと考えられます。
自分に支払能力があるか知りたい
銀行から借りた不動産投資ローンなど、負債を問題なく返済できるだけの支払能力があるかを知るためには、流動比率を求めましょう。以下の式で計算できます。
基本的には、流動比率が100%以上確保できていれば、資金繰りに大きな問題はないと言えます。高いに越したことはありませんが、まずは100%を常に上回れるようにしましょう。
また、現金や預金など換金性が高い(すぐにお金にできる)資産をベースにした支払能力を知りたい場合は、以下の式で当座比率を求めます。
一般的に、80%以下であれば要注意水準に達していると判断されるため、まずは80%超をキープできるよう常に心掛けてください。
事業としての安定性を知りたい
自分の不動産投資がうまくいっているか、事業としての安定性を知りたい場合は、自己資本比率に着目しましょう。これは、総資本に対する自己資本の割合のことで、以下の式で計算できます。
この数値が高いほど、将来返済しなくていけない部分=負債は小さいと考えられるため、事業としての安定性も高いといえます。逆に、自己資本比率が低いと財務の健全性が低い、つまり不動産投資がうまくいっておらず、利益が生み出せていないと判断されるため注意が必要です。
また、自己資本比率が高かったとしても、現金が少ない、固定資産があまりに多い状態だった場合は安心できません。すぐに資金が必要になっても調達できず、ビジネスチャンスを逃したり、最悪の場合倒産したりする可能性もあります。
うまく利益を生み出せているか知りたい
資本のうち、自分で出資した資本=自己資本からどの程度利益を生み出せているか知りたい場合は、自己資本利益率を求めましょう。以下の式で求められます。
この数値が高ければ、自分が出資した資金がうまく運用できていて、利益を生み出せているということです。業種や業界によっても異なりますが、一般的には8~10%が目安と言われています。
一方で、マイナスになっている場合、債務超過に陥っている、もしくはそのリスクが高いと判断されるため、まずはマイナスにならないよう注意しましょう。
融資を受け過ぎていないか知りたい
自分が融資を受け過ぎていて、財務の健全性が損なわれていないかを知るためには、以下の式で負債比率を求めましょう。
これは、自己資本に対して負債(他人資本)がどのぐらいあるのか表す数値です。負債比率が小さいほど、自己資本の割合が大きく、財務が健全な状態にあると考えられます。ただし、単に事業活動に対し消極的で、借入もしていなければ低くなるのも事実である点に注意してください。
詳しくは後述しますが、貸借対照表をはじめとした財務諸表は、会計ソフトを使えば簡単にできます。しかし、取引が発生したときに仕訳を記録するところから、どのようなプロセスを経て貸借対照表を仕上げていくのか知っておきましょう。
もちろん、難しく考え過ぎずあくまで「こういうものなのか」といった程度に考えてもらえれば構いません。
①仕訳帳に取引を記載する
まず、取引が発生したら仕訳を仕訳帳に記入します。仕訳とは、勘定科目を使い、お金やものの動きを区分けして記録する作業です。ここで重要になる考え方として「取引を原因と結果に分ける」ことが挙げられます。
例えば、6月30日に車を100万円で購入し、現金一括で支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
最初は慣れないかもしれませんが、自分で経理作業をしていくなら重要になる考え方であるため、徐々に慣れていきましょう。
なお、仕訳をスムーズにできるようにするには「何が減って何が増えたか」に着目してみることです。最初は、以下の主要な分け方をマスターしましょう。
| 項目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 資産 | 資産の増加 | 資産の減少 |
| 負債 | 負債の減少 | 負債の増加 |
| 純資産(自己資本) | 純資産の減少 | 純資産の増加 |
| 費用 | 費用の増加 | 費用の減少 |
| 収益 | 収益の減少 | 収益の増加 |
また、一般的な仕訳帳として以下のようなものを使うため、手書きや表計算ソフトで作成する場合は参考にしてください。
| 日付 | 摘要 | 元丁 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
なお、それぞれの項目には以下の情報を書き込みます。
- 日付:取引が発生した日付
- 摘要:取引の詳細や相手先の情報
- 元丁:総勘定元帳(後述)の転記先
例えば、6月30日に車を100万円で購入した場合は、以下のように記入します。※元丁は省略
| 日付 | 摘要 | 元丁 | 借方(円) | 貸方(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | (車両運搬具) | 1,000,000 | |||
| (現金預金) | 1,000,000 | |||||
②総勘定元帳に転記する
取引を仕訳として仕訳帳に記録したら、すべての取引を勘定科目ごとに整理していくため、総勘定元帳に転記します。
より厳密には以下の流れで進めますが、まずは「そういうものか」程度に考えてもらえれば構いません。
- 取引が発生する
- 日付ごとに仕訳帳に記録していく
- 勘定科目ごとに勘定口座を作成する
- 仕訳帳から仕訳を総勘定元帳に転記する
なお、総勘定元帳は一般的には以下のようになっています。表計算ソフトやノートで作成する場合は参考にしてください。
| 日付 | 摘要 | 仕丁 | 借方 | 日付 | 摘要 | 仕丁 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちなみに、総勘定元帳における「仕丁」には、仕訳日計表(1日に起票された伝票の仕訳を集計した表)のページ数を書きます。
③試算表を作成する
決算を迎えたら、貸借の金額にずれがないかを確認するために試算表を作成します。なお、試算表は、合計試算表、残高試算表、合計残高試算表の3つに分類することが可能です。
合計試算表
総勘定元帳における各勘定科目の借方と貸方の合計をまとめたものです。総勘定元帳の借方、貸方の合計を求めたうえで、合計試算表に転記して作成します。
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|
| 〇〇〇 | 現金 | 〇〇〇 |
| 〇〇〇 | 当座預金 | 〇〇〇 |
| 〇〇〇 | 商品 | 〇〇〇 |
| 〇〇〇 | 買掛金 | 〇〇〇 |
| 資本金 | 〇〇〇 | |
| 売上 | 〇〇〇 | |
| 未払金 | 〇〇〇 | |
| 〇〇〇 | 給料 | |
| 〇〇〇 | 家賃 | |
| 〇〇〇 | 消耗品費 | |
| 〇〇〇 | 通信費 | |
| … | ||
| 〇〇〇 | 合計額 | 〇〇〇 |
残高試算表
個々の勘定科目ごとに残高のみを一覧化したものです。勘定科目ごとに借方・貸方の合計を比較し、いずれか大きい方から小さい方を差し引いた差額を転記して作成します。
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|
| 〇〇〇 | 現金 | |
| 〇〇〇 | 当座預金 | |
| 〇〇〇 | 商品 | |
| 買掛金 | 〇〇〇 | |
| 資本金 | 〇〇〇 | |
| 売上 | 〇〇〇 | |
| 未払金 | 〇〇〇 | |
| 〇〇〇 | 給料 | |
| 〇〇〇 | 家賃 | |
| 〇〇〇 | 消耗品費 | |
| 〇〇〇 | 通信費 | |
| … | ||
| 〇〇〇 | 合計額 | 〇〇〇 |
合計残高試算表
合計試算表と残高試算表を組み合わせたものです。勘定科目ごとに借方合計と貸方合計を合計部分に転記したうえで、各々の合計額を差し引いた部分を残高に記載します。
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 残高 | 合計 | 合計 | 残高 | |
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 現金 | 〇〇〇 | |
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 当座預金 | 〇〇〇 | |
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 商品 | 〇〇〇 | |
| 〇〇〇 | 買掛金 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | |
| 資本金 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | ||
| 売上 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | ||
| 未払金 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | ||
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 給料 | ||
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 家賃 | ||
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 消耗品費 | ||
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 通信費 | ||
| … | ||||
| 〇〇〇 | 〇〇〇 | 合計額 | 〇〇〇 | 〇〇〇 |
④貸借対照表および損益計算書を作成する
試算表ができたら、決算整理仕訳を行って対策対照表を仕上げていきます。資産・負債・純資産に属する勘定科目を抜き出してまとめていく形です。
一方、収益や費用をまとめあげていくと損益計算書ができます。
なお、決算整理仕訳とはその決算期末のときまで処理がなされないままになっていた取引を整理するために行う仕訳のことです。具体的には以下の仕訳を行います。
- 現金の過不足の処理
- 未使用のままの消耗品の処理
- 固定資産の減価償却
- 有価証券の評価替え
- 貸倒引当金の設定
- 費用と収益の繰延・見越し
- 売上原価の算定
- 借地条件の変更及び増改築の許可(借地借家法17条)
- 借地契約の更新後の建物の再築の許可(借地借家法18条)
- 定期借地権(借地借家法22条)
- 事業用定期借地権等(借地借家法23条)
- 建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)
実際に貸借対照表を作る際、用いられる一般的な方法は以下の3つです。
- 手書き
- 表計算ソフト
- 会計ソフト
ここでは、それぞれの方法のメリット・デメリットも含めて解説します。
手書き
一般的なノート等を用いて、手書きで貸借対照表を作成する方法です。会計ソフトや表計算ソフトがなくてもすぐに始められるうえに、費用はかかりません。しかし、時間がかかるうえに、書いた内容が誤っていた場合の修正や更新が難しくなります。手書きで帳簿をつけていた経験がある、簿記の資格を持っているなど、特殊な事情がない限りは、あえて手書きで作るメリットは薄いでしょう。
表計算ソフト
ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトを使って貸借対照表を作成する方法です。パソコンにこれらの表計算ソフトがインストールされていれば、比較的簡単かつ低コストで始められます。また、テンプレートも多数用意されているうえに、カスタマイズも容易です。

ただし、カスタムする場合はテンプレートに組み込まれている関数が破損しやすい点に注意しなくてはいけません。また、処理すべきデータが多いと処理の段階でエラーを起こすリスクが高くなります。普段から表計算ソフトを使いこなしている人以外は、できれば使わないほうが無難かもしれません。
会計ソフト
会計ソフトは、仕訳を入力していくと自動的に仕訳帳への記載、総勘定元帳への転記、試算表の作成から貸借対照表・損益計算書の作成まで自動化できるソフトウエアのことです。従来からあるパッケージ型に加え、昨今はクラウド型のものも広く普及しています。基本的な仕訳を理解していれば簡単に使えるものが多いうえに、エラーに関してはアラートが出るため、ミスを防げるのがメリットです。ただし、パッケージ型なら購入時に、クラウド型なら毎年もしくは毎月使用料を払わないといけません。また、最初は操作に慣れる必要があるため、パソコンに抵抗があるとやや大変な部分もあります。
それでも、操作を覚えれば短時間で正確な会計処理ができるようになるため、3つの中では最もおすすめする方法です。ちなみに、不動産投資の帳簿作成のために導入した会計ソフトの費用は、必要経費として処理できます。
貸借対照表は、企業もしくは事業主が持つ資産・負債・純資本の残高をまとめた表です。慣れないと難しく感じるかもしれませんが、まずはどこに何が書かれているかを理解するよう努めましょう。
貸借対照表のさまざまな数値に着目することで、地震の不動産投資が事業としてうまくいっているのか、ある程度客観的にチェックできます。不動産投資も他の事業と同様、常に状況をモニタリングし、改善を繰り返していくことが重要です。貸借対照表はそのための重要なデータになるため、上手に使いこなしてください。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30~18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.


