ペットの無断飼育は契約違反! 賃貸契約を解除して入居者を追い出すには? | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産
ペットの無断飼育は契約違反! 賃貸契約を解除して入居者を追い出すには?
2025-09-16

2020年初頭から新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、いわゆる「ペットブーム」が起きました。2025年の現在、幾分落ち着きはしたものの、ペットとの暮らしを望む人は一定数います。
それ自体は悪いことではありませんが、飼育が禁止されている場所で飼うのはやはりタブーです。そこで今回の記事では「自分が所有する物件で、ペットを無断で飼っている入居者がいた場合、「契約違反を理由に退去を求められるか」について解説します。
大前提として、入居者がペットを飼っていたとしても、正当な根拠なく追い出すことはできません。そのため、自分が所有する物件でペットを飼ってほしくないなら、何をすれば良いのかをまずは把握しましょう。
賃貸借契約に「ペット禁止特約」を設ける
自分の物件をペット不可物件にしたいなら、賃貸借契約に「ペット禁止特約」を設けるのが現実的な対応となります。つまり、「室内で犬、猫その他の動物は飼えません」という旨を特約事項や入居者の心得、管理規約などに盛り込まなくてはいけません。
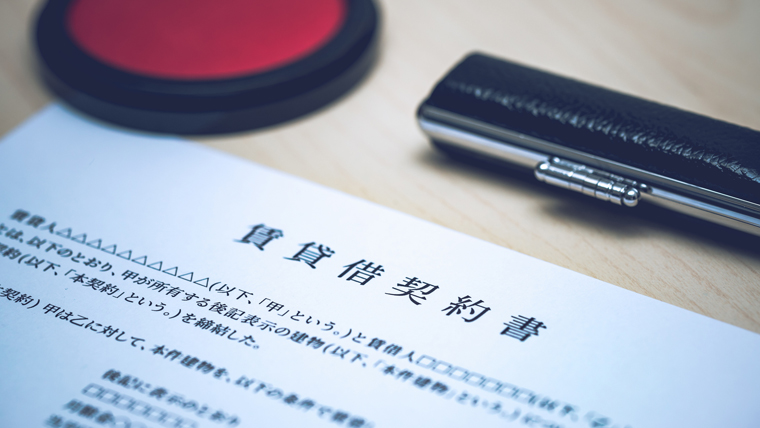
なお、ハムスターや熱帯魚など、鳴き声がせず、周辺環境への影響も小さい動物の飼育までを禁止したい場合は「動物の飼育は一切お断りします」など、明確に記載しましょう。
ペット禁止特約を盛り込んだうえで賃貸借契約を締結していたにもかかわらず、隠れてペットを飼っていた入居者を追い出せるかは、ケースバイケースです。ここでは、具体的な判断基準について解説します。
信頼関係破壊理論に基づいて判断
禁止されているにもかかわらずペットを飼っていた入居者の扱いについては、 信頼関係破壊理論に基づいて判断されます。これは、賃借人の債務の不履行があっても、信頼関係を破壊しない程度の不履行であったなら、契約は解除できないという考え方を指します。
たしかに、ペット飼育禁止特約が契約に盛り込まれている状態でペットを飼うのは契約違反であるため、それを信頼関係が破壊された状態として扱い、契約を解除できる余地はあるでしょう。
実際に判例でも「動物等飼育禁止の特約がある以上は、賃借人として特約は守るべき」という判断が示されたことがあります(東京地裁平成7年7月12日判例)。
ただし、裁判にまで発展した場合、信頼関係が破壊されていたかどうかは、ペットの種類や飼育数、飼育状況によって判断されます。そのため、単にペットを飼っていたというだけで賃貸借契約を100%解除できるとは言い切れない点に注意が必要です。
※参考:公益財団法人 不動流通推進センター
現実的には、飼い主の飼い方が悪く、近隣からクレームが相次いでいたなどの理由でペットの飼育が発覚した場合、または問題が看過できない状態であった場合には、信頼関係が破壊されたことを理由に賃貸借契約を解除できると考えられます。
特約が存在しない場合は状況次第
ペット禁止特約が契約に特段盛り込まれていなかった場合は、部屋でペットを飼うこと自体は可能です。しかし、蛇などの危険な動物を飼っていたり、トイレの不始末や他の入居者に吠えるなど、飼育状況に問題があるなら、契約に定められた使用方法に反するものとして、賃貸借契約の解除はできると考えられます。
ここからは、ペットを飼っている入居者を見つけた場合の対応について詳しく解説します。なお、前提として「賃貸借契約にペット禁止特約を盛り込んでおり、その前提で契約している」入居者の場合と考えてください。
まずは該当する入居者に確認する
まず、ペットを飼っている疑いがある入居者を見つけた場合は、該当する入居者に確認しましょう。他の入居者から通報があった場合も同様です。

ペットを飼っているのが発覚するきっかけの例
実際のところ、ペットの無断飼育が発覚する経緯はさまざまです。一般的なマンション・アパートで考えられる、主な発覚ルートの例をいくつか紹介します。
<ペットの無断飼育が発覚するルートの例>
- エレベーターホールでペットを連れている人を見かけた
- 窓から外をのぞいているペットを見かけた
- どこかの部屋からペットの臭いがする
- ドライフードやシーツなどペット用品のゴミが捨てられている
- どこかの部屋から犬や猫の鳴き声が聞こえる
証拠収集が重要
他の入居者からの報告があったからといって、証拠もないのにいきなり該当する入居者に連絡するのは得策ではありません。万が一間違いだった場合、報告された入居者から反発を招く可能性があるためです。
また、確固たる証拠もないまま入居者に退去を求めたとしても「知人から預かっただけ」など、飼育の事実自体を認めない可能性が出てきます。自身にとって不利な展開になりかねないため、まずは証拠を収集してから入居者との交渉に臨みましょう。
退去を命じるか継続入居を許可するかを検討する
ペットを無断飼育に関する証拠を入手し、該当する入居者にも事実を確認したら、退去を命じるか、継続入居を許可するかを検討しましょう。賃貸借契約にペット禁止特約が盛り込まれている場合は、その特約に違反したものとして退去を求める方向で動くのが一般的です。

ただし、入居者が反発してくる可能性もあるため、まずは親族の家に預けるなどの形で飼育を中止できないか要望を出しましょう。要望に応えて飼育を中止した場合は、それ以上退去を求める必要もありません。
一方、入居者が飼育を止めない場合は、退去を求めていくことになります。その場合に重要なのは、退去期限を明確に示すことです。明確な期限を示さないと飼育が長引きかねないので注意しましょう。
また、これらのやり取りは証拠に残すという意味で、内容証明郵便など書面によることを強く推奨します。
退去に応じない場合は強制退去も要検討
提示した期限までに退去しない場合、内容証明郵便により賃貸借契約解除の予告通知をする必要があります。その後、実際に賃貸借契約を解除します。
さらに、賃貸借契約を解除した後も入居者が退去しない場合は、裁判所で明渡請求の訴訟による解決を図るのが現実的です。訴訟で原告(大家)が勝訴すれば入居者が退去する可能性が高くなりますが、万が一退去しなかった場合は、強制執行を申し立てたうえで、部屋の家財道具をすべて撤去し、鍵を交換することになります。
ここまでの事態になると、弁護士などの専門家に依頼するのが現実的になるうえに、相応の費用と手間もかかります。なるべくなら早い段階で、話し合いでの解決を目指しましょう。
原状回復費用を請求する
入居者を退去させる形で解決を図る場合は、退去にあたって原状回復費用を請求しなくてはいけません。ただし、根拠もなく高額な費用を請求するのは、入居者とのトラブルにつながるため注意が必要です。
そのため、現実的には管理会社が提携している工務店等に見積もりを取ってもらい、その見積もりに基づいて費用を請求しましょう。
継続入居を許可するなら条件を交渉する
飼っているのが熱帯魚やハムスターなどの小動物であるなど、ペットを飼育し続けていても他の入居者の不利益につながる可能性が低いのであれば、あえて継続入居を許可し続けるのも選択肢の一つといえます。

空室にはならない以上、入居率の低下を防げるとともに、その入居者との信頼関係を構築でき、長期入居につながる可能性もあるためです。
一方で、部屋が傷む可能性はあるため、敷金を追加で払う、もしくは家賃を通常のケースより高くするなど、将来の原状回復に備えて条件を交渉する必要があります。
また、他の入居者とのトラブルを防ぐため、以下の配慮をするよう入居者に求めなくてはいけません。
- 共用部では必ずケージに入れる
- 放し飼いはさせない
- 臭いが共用部に漏れないよう、掃除や手入れを徹底する
- 予防接種が必要な動物であれば、定期的に受けさせる
部屋に居座るのは「不退去罪」、家財道具を勝手に処分するのは「窃盗罪」や「住居侵入罪」に問われる可能性があります。文中で触れたように、退去を求めるにしても、証拠を入手したうえでまずは話し合いから始めましょう。
早い段階で弁護士などの専門家に相談し、どのように解決すれば良いかアドバイスを受けるのも重要です。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30~18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.


