不動産投資の決算書はどこを見られる? 金融機関のチェックポイントを解説 | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産
不動産投資の決算書はどこを見られる? 金融機関のチェックポイントを解説
2025-08-01
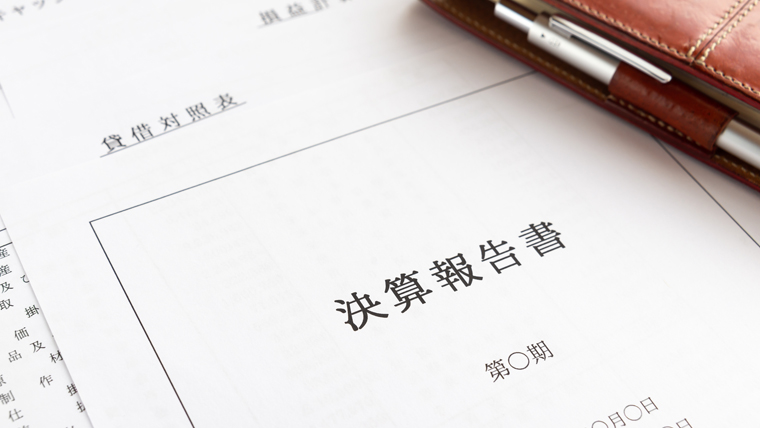
不動産投資も一種の事業である以上、本当に利益が出ているのか定期的にチェックしなくてはいけません。そのために役立つのが決算書です。
法人として不動産投資に取り組む場合はもちろん、個人の場合も作成が求められることがあるため、基本的な知識は習得しておきましょう。
この記事では、不動産投資において最低限作らなくてはいけない決算書3種類(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)について、基本的な知識に触れつつ、金融機関がチェックするポイントも解説します。
不動産投資において、個人・法人が作成する必要がある決算書は以下の通りです。
- 損益計算書(P/L)
- 貸借対照表(B/S)
- キャッシュフロー計算書(C/F)
それぞれの役割を確認していきましょう。
①損益計算書(P/L)
損益計算書とは、法人もしくは個人の収入や支出を1つの表としてまとめたものです。英語では「Profit and Loss Statement」というため、「P/L」という略称が使われることがあります。

1年間の収益性・成長性など経営成績を示す書類であり、大きく分けると以下の3つの部分から構成されているのが大きな特徴です。
- 収益(売上高):事業の運営によりどのぐらいの収入が得られたか
- 費用(コスト):事業を運営するためにどの程度の経費がかかったか
- 純利益(最終的な利益):収益と費用の差額
損益計算書を簡単な図で表すと、以下のようになります。
| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 600 | 売上高 | 1,000 |
| 広告費 | 100 | ||
| 支払利息 | 20 | ||
| 固定資産売却損 | 40 | ||
| 法人税等 | 140 | ||
| (当期純利益) | 100 |
上記の図のような表記の仕方を「勘定式」というのに対し、以下のように必要事項を上から下に並べていく「報告式」という表記も用いられます。
| 売上高 | 1,000 |
|---|---|
| 売上原価 | 600 |
| 売上総利益 | 400 |
| 販売費および一般管理費 | 100 |
| 営業外費用 | 20 |
| 経常利益 | 280 |
| 特別損失 | 40 |
| 税引前当期純利益 | 240 |
| 法人税等 | 140 |
| 当期純利益 | 100 |
なお、損益計算書では利益を次の5段階に分けて計算することも覚えておきましょう。
| 売上総利益(粗利益) | 「売上総利益=売上高 - 売上原価」として計算。商品やサービスの提供など、本業により得られた利益を表す。なお、売上原価とは商品の仕入や製造にかかった費用のこと。 |
|---|---|
| 営業利益 | 「営業利益=売上高 - 売上原価 - (販売費及び一般管理費/販管費)」として計算。販売費とは、商品・サービスの広告活用などの販売促進活動にかかった費用。一般管理費は、オフィスの家賃や水道光熱費、バックオフィス部門の従業員にかかる賞与や給与などが該当。 |
| 経常利益 | 「経常利益=営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用」として計算。営業外収益とは、受取利息など本業以外の理由で得られた収益。一方、営業外費用とは借入金の利息など本業とは関係なく発生する費用。 |
| 税引前当期利益 | 「税引前当期純利益=経常利益 + 特別利益 - 特別損失」として計算。特別利益とは、社用車を売って得た利益など通常の経営とは無関係に発生した利益を指す。同様に、特別損失とは、通常の経営とは無関係に発生した損失のことで災害により生じた損失などが当てはまる。 |
| 当期純利益 | 「当期純利益=税引前当期純利益 - (法人税 + 住民税 + 事業税) ± 法人税等調整額」として計算。 |
つまり、売上総利益が高ければ事業(例:不動産投資)がそれなりに順調であることが考えられます。一方、売上総利益が高くても、販売費および一般管理費もかかっていれば営業利益、経常利益、税引前当期利益や当期純利益が減ってしまうかもしれません。
また、売上総利益があまり出ていなくても、営業外収益が大きければ、経常利益はそこまで少なくならない可能性もあります。重要なのは「どういう理由でどれだけ収入がある、費用がかかっているか」を可視化することであり、そのために損益計算書は非常に役立つはずです。
なお、損益計算書を作成する基本的な流れは、以下の通りです。
- 決算整理仕訳を行う
- 総勘定元帳に転記する
- 試算表を作成する
- 試算表から総勘定元帳に転記を行う
②貸借対照表(B/S)
貸借対照表とは、企業もしくは個人の特定の時点における財産、権利、義務の所有状況を示したものです。英語では「Balance sheet」というため、「B/S」という略称が使われることがあります。
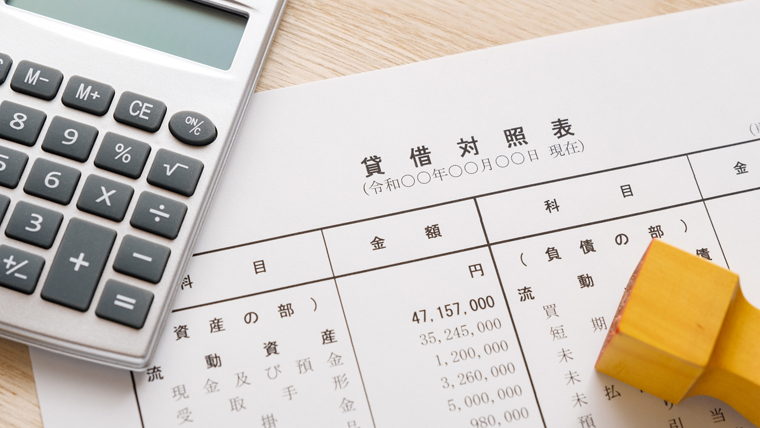
貸借対照表の記載例(勘定式)は以下の通りです。
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 流動負債 | ||
| 現金預金 | 10,000 | 支払手形 | 10,000 |
| 受取手形 | 20,000 | 買掛金 | 20,000 |
| 売掛金 | 40,000 | 短期借入金 | 20,000 |
| 有価証券 | 10,000 | 未払金 | 10,000 |
| 商品 | 4,000 | その他 | 20,000 |
| その他 | 20,000 | 固定負債 | |
| 固定資産 | 長期借入金 | 100,000 | |
| 土地 | 100,000 | 社債 | 60,000 |
| 建物 | 60,000 | その他 | 4,000 |
| 機械装置 | 20,000 | 純資産の部 | |
| その他 | 60,000 | 株主資本 | |
| 繰延資産 | 資本金 | 100,000 | |
| 開業費 | 10,000 | 資本剰余金 | 4,000 |
| その他 | 2,000 | 利益剰余金 | 8,000 |
| 資産合計 | 356,000 | 負債純資産合計 | 356,000 |
なお、貸借対照表を大きく分けると、次の3つの部分から構成されることを覚えておきましょう。
| 資産の部 | 会社もしくは個人として調達した資金をどのように使っているか(資本の運用形態) |
|---|---|
| 負債の部 | 会社もしくは個人として、どのように他者から資金調達しているか(他人資本の調達源泉) |
| 純資産の部 | 資産と負債の差額として計算される正味財産の状況(自己資本の調達源泉) |
また、資産の部は「流動資産」「固定資産」「繰延資産」に分けられます。
| 流動資産 | 1年以内に現金化できる資産。現金、普通預金、当座預金、有価証券、受取手形、売掛金などが含まれる。 |
|---|---|
| 固定資産 | 1年を超えて現金化されず、長期にわたり使われ続けることが想定される資産。土地や建物、設備、営業権、商標権などが含まれる。 |
| 繰延資産 | 流動資産、固定資産のいずれにも当てはまらないもの。開業費など本来は費用であるが、一度資産に計上し、その後数年間にわたって償却される費用が含まれる。 |
同様に、負債の部も1年以内の返済を予定している「流動負債」と、1年を超えて返済を予定している「固定負債」に分類可能です。
| 流動負債 | 返済期限が1年以内に到来する負債のことで、支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、前受金、預り金、仮受金などが含まれる。 |
|---|---|
| 固定負債 | 返済期限が1年を超えて到来する負債のことで、長期借入金や社債、退職給付引当金、貸倒引当金などが含まれる。 |
また、資本金・資本剰余金・利益剰余金には、以下のものが含まれます。
| 資本金 | 株主からの払込金などにつき、「資本金」として会計処理した部分を指す。 |
|---|---|
| 資本剰余金 | 株主からの払込金などであるが、資本金ではない部分を指す。「資本準備金」と「その他資本剰余金」にさらに分類可能。 |
| 利益剰余金 | 株主の配当などに際し、法律で積立が求められる「利益準備金」と、その他利益剰余金(任意積立金、繰越利益剰余金)に分類可能。 |
なお、貸借対照表を作成する基本的な手順は以下のとおりです。
- 取引が発生したら、仕訳帳に記録する
- 取引内容を借方・貸方に振り分ける
- 勘定科目ごとに総勘定元帳に転記する
- 総勘定元帳に記載されている借方・貸方の合計金額、残高を試算表に転記する
- 決算整理仕訳を行う
- 貸借対照表(B/S)を作る
③キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)とは、一定の会計期間(基本的に1年間)の現預金の動きをルールに従って表示した決算書類です。上場企業など所定の条件を満たす法人であれば作成する義務がありますが、それ以外の法人や個人事業主に作成義務はありません。
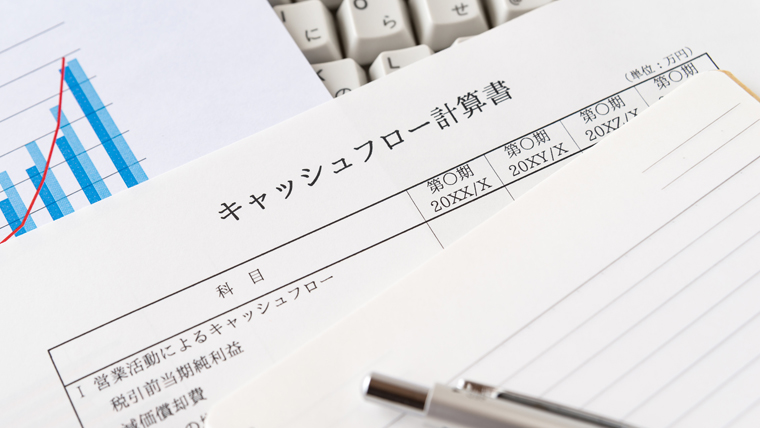
しかし、キャッシュフロー計算書を作ることで、なぜ現預金が変動したのかを正確に把握できるようになるため、可能であれば作ってみましょう。
キャッシュフロー計算書の作成例は以下の通りです。
| ①営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 税引前当期純利益 | (具体的な金額が入る) |
| 減価償却費 | |
| 売上債権の減少(増加) | |
| 投資有価証券売却損益 | |
| 棚卸資産の減少(増加) | |
| 買入債務の増加(減少) | |
| ②投資キャッシュフロー | |
| 固定資産の減少(増加) | |
| 投資キャッシュフロー | |
| フリーキャッシュフロー(①-②) | |
| ③財務キャッシュフロー | |
| 借入金・社債の増加(減少) | |
| 配当金支払い | |
| 財務キャッシュフロー | |
| キャッシュ増加(①+②+③) | |
| キャッシュ期首残 | |
| キャッシュ期末残 | |
以下の3つの区分に分けることで現金などの流れを表すため、正確に理解しましょう。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 正確には「営業活動によるキャッシュフロー」。本業である事業の運営により、どれぐらいの現金を稼得したかを表す。仕入、売上に使った金額が関連する。 |
| 投資キャッシュフロー | 正確には「投資活動によるキャッシュフロー」。事業に関連して行った投資により、どれだけの現金が出入りしたかを表す。有形固定資産の取得、売却により出入りした現金が関連する。 |
| 財務キャッシュフロー | 正確には「財務活動によるキャッシュフロー」。資金の調達、借入金の返済などの財務活動により出入りする現金を表す。金融機関からの借入れ、株式・社債の発行費が関連する。 |
また、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを差し引いたものを「フリーキャッシュフロー」と言います。これは、企業もしくは事業において自由に使える現金の量を示しており、マイナスになると企業・事業の成長性・安定性の悪化が懸念されるため注意しなくてはいけません。
なお、キャッシュフロー計算書には「直接法」と「間接法」の2つの表示方法があります。営業キャッシュフローでは間接法、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローでは直接法を使うのが一般的です。
| 直接法 | 主要な取引ごとにキャッシュフローの総額を表す。 |
|---|---|
| 間接法 | 税引前当期純利益に以下の3つの項目を加減算して、営業キャッシュフローを表す ・キャッシュの動きを伴わない項目や営業活動にかかる資産・負債の増減 ・投資キャッシュフローに関連して発生した損益項目 ・財務キャッシュフローに関連して発生した損益項目 |
サラリーマン大家、つまり個人事業主かつ副業として不動産投資に取り組んでいる人は、決算書を作るべきか迷うかもしれません。本業との兼ね合いにもよりますが、可能な限り決算書は作るべきです。その税務・資金調達・経営の観点から理由を解説します。
基本的には「作るべき」
可能な限りは作るべき理由を一言でまとめると「何かと得することが多いから」です。
大前提として、個人事業主の場合、青色申告もしくは白色申告のいずれかで、毎年確定申告をしなくてはいけません。(所得税の)確定申告とは暦年すなわち1月1日~12月31日までの1年間の収益と費用を求め、翌年の2月16日~3月15日(当日が土日祝日の場合は休み明けの平日)の間に税務署へ申告・納税する制度です。サラリーマン(会社員)として働いている場合でも、副業により得られた所得が年間20万円を超えたなら、確定申告をする必要が出てきます。

ただし、白色申告を選択している場合は、確定申告の際に「収支内訳書」を提出すれば良く、貸借対照表を含めた決算書を作る必要はありません。
しかし、不動産投資における経営成績や財務状況をより客観的に把握するためには、決算書を作るのが望ましいと言えます。また、金融機関からの融資を希望する際は、審査書類として決算書を提出するよう求められることがほとんどです。すべて自己資金で続けていくつもりであれば別ですが、現実的には決算書を作らざるを得ないでしょう。
なお、青色申告は白色申告に比べ高い節税効果が見込めます。
主要な違いを簡単な表にまとめたので、参考にしてください。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 | |
|---|---|---|---|
| 税務署への届出 | 不要 | 必要 | |
| 控除 | なし | 10万円 | 65万円(※1) |
| 帳簿の種類 | 単式簿記 | 複式簿記 | |
| 決算書の作成 | 収支内訳書 | 貸借対照表・損益計算書 | |
| 一部記入 | 全部記入 | ||
| 赤字の繰越 | できない | できる | できる |
勤務先との就業規則との兼ね合いで問題がなさそうなら、青色申告事業者になることも検討しましょう。税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。
不動産投資で融資を受ける際、金融機関は決算書を融資の可否を判断する上での重要な参考資料としています。
基本的には、融資をしても問題ないか推し量るために、すべての項目をチェックされると考えて構いません。

ここでは、貸借対照表、損益計算書についてチェックされるポイントのうち、特に重要なものに絞って解説するので参考にしてください。
貸借対照表で見られるポイント
まず、貸借対照表で見られる主要なポイントとして、以下の2点が挙げられます。
繰越利益剰余金の金額
1つ目は、繰越利益剰余金の金額です。繰越利益剰余金は過年度の利益の積上額であるため、マイナスになっていると過去の赤字が解消しきれていないという意味になります。不動産投資に限らず事業を開始した初年度は何かと出費が多い以上、ある程度の赤字は致し方ありません。
しかし、次年度以降も赤字のままで、繰越利益剰余金もマイナスのままだと、融資を受けるのは非常に厳しくなります。不動産投資を始めるなら、まずは2年目以降黒字に転換することを目指して事業計画を立てましょう。
建物・土地の金額
2つ目は、建物・土地の金額です。特に、現時点での売却価格が、貸借対照表に記載された金額を大幅に上回らないか注意しましょう。高く売れれば売れるほど得られる利益は多くなるので、一見良いことに感じるかもしれません。しかし、得られた利益が大きければ、その分支払うべき税金も大きくなります。
状況次第では将来的に多額のキャッシュが出て行く事態になりかねないため、注意が必要です。例え黒字だったとしても、税金が払えなくなる状態では到底事業を続けられません。その点を懸念して、金融機関がマイナスの評価をすることは十分に考えられます。
損益計算書で見られるポイント
一方、損益計算書ではどこを見られるのでしょうか。
当期純利益の金額
金融機関の担当者は、貸借対照表と同様、損益計算書の各部分に目を光らせています。その中でも特に重要なのが「当期純利益の金額」です。これがマイナスだと、事業として赤字であることを意味するため、審査において不利になるかもしれません。
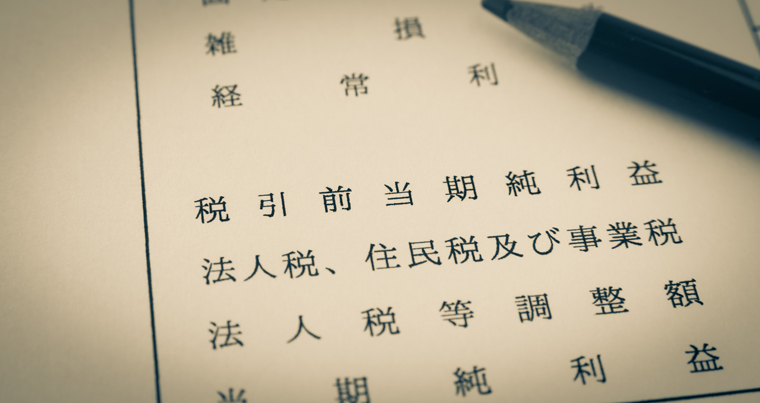
ただし、地震などの災害で所有物件が損傷したなど、事業運営の良し悪しに関係しない原因で赤字になることも考えられます。万が一赤字になってしまった場合は、金融機関の担当者にその理由を説明できるようにしておきましょう。
また、法人であれば計上する減価償却費の額を一定の範囲内で調整できます。どうしても赤字になりそうなら、減価償却費をあえて全額計上しないで、当期純利益をプラスにすることも可能です。
ただし、このような方法で無理やり赤字を回避したことが発覚すると、金融機関によってはネガティブな評価を下すことがあります。事前に税理士などの専門家にも相談してみましょう。
なお、個人事業主として不動産投資をしている場合は、減価償却費を全額計上しなくてはいけないため、この方法は使えません。
決算書は、不動産投資をはじめとした事業を営む上では、非常に重要な書類です。正確に作成することで、自分の不動産投資のやり方で利益が出せているか、問題点が生じていないかを可視化できます。面倒に感じるかもしれませんが、ぜひ作ってみましょう。
一見すると難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトを使えば、仕訳を入力するだけで自動的に損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書を作ってくれます。基本的には指示に従って入力していけば良いため、まずは気軽にチャレンジしてみましょう。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30~18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.


