不動産投資の初期費用はいくら? 費用の内訳や抑えるための方法も解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産
不動産投資の初期費用はいくら? 費用の内訳や抑えるための方法も解説!
2025-01-24

不動産投資を始める際は、多額の初期費用がかかります。初期費用には多くの項目があり、内容も複雑ですが、目安額や計算方法を理解できると資力に合った物件選びや無理のない投資計画の立案が可能になります。
こうした初期費用の重要性を踏まえ、本記事では、不動産投資にかかる初期費用の目安や内訳について解説します。ワンルームマンション投資と一棟マンション投資にかかる初期費用をシミュレーション結果や不動産投資の初期費用を抑える方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
不動産投資を始める際は自己資金10%に諸経費を加えた約16%の初期費用が必要です。
そこから逆算すると、1億円の収益物件を購入するには、最低でも最初に1,600万円程度のまとまった資金が必要になります。
ただし、最近は20%以上の自己資金を求められるケースが増えてきました。実際、信金やノンバンクは20%程度の自己資金を求められます。自己資金を10%で抑えられるのは、地銀など限られた銀行だけです。

必要な自己資金額は個人の属性によっても、左右します。自己資金の多寡を左右する要素は年収や資産額などの個人の属性、駅距離や築年数などの物件の属性です。この2つの属性がよければ、銀行による担保評価が高くなって借入額が大きくなり、結果として自己資金額を減らせます。
自己資金額を減らしたうえで、借入額を増やすうえでは、銀行とのつながりも重要です。たとえば、信用金庫や日本政策金融公庫などのマイナーな金融機関とのつながりをうまく生かすことで、本来出るはずもない好条件の融資が出る場合もあります。
ここからは、不動産投資にかかる初期費用の内訳について解説します。内訳を一覧表にまとめると、次のとおりです。
| 内訳 | 概要 |
|---|---|
| 物件の頭金 | 物件購入にあたって必要となる自己資金。 |
| 不動産仲介手数料 | 売買したときに不動産仲介会社に支払う手数料 |
| 銀行事務手数料 | 融資を受ける際に銀行に支払う事務手続きの手数料 |
| 融資保証料 | 金融機関から融資を受ける際、保証会社に保証人になってもらうための費用 |
| 登記費用(登録免許税・司法書士報酬) | 登録免許税 登記手続きの際に国に納める税金 司法書士報酬 司法書士に支払う報酬額 |
| 各種税金(不動産取得税・印紙税・固定資産税・都市計画税) | 不動産取得税 土地や家屋などの不動産を新たに取得した際に一度だけ課税される地方税(都道府県税) 印紙税 不動産売買契約書に貼付する収入印紙代 固定資産税 土地や家屋などの固定資産にかかる税金 都市計画税 市街化区域内に所在する土地と家屋に課される税金 |
| 火災保険料・地震保険料 | 火災保険料 物件が火災の被害に遭った際の損害を補償する火災保険の保険料 地震保険料 物件が地震の被害に遭った際の損害を補償する火災保険の保険料 |
各費用の目安については、次項より説明します。
物件の頭金
物件の頭金は収入や勤務先、物件の担保評価額によって変化しやすい費用ですが、おおよそ物件価格の10%が目安です。ただ、金融機関によっては20%以上の頭金を求められる場合があります。
頭金が多いと初期費用が大きくなりますが、頭金が多いに越したことがありません。頭金が多いと、資産評価も高くなり、融資が通りやすくなるためです。

もし頭金を使う必要がない場合でも、使わずに手元に残しておけば安心です。不動産投資を進めるなかで必ず頭金が大きい物件が出てきます。その将来のためにお金を残しておくのも賢い戦略の1つといえるでしょう。
不動産仲介手数料
不動産仲介手数料は、物件価格に応じて段階的に計算されます。
| 不動産価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 800万円以下 | 最大33万円 |
| 801万円以上 | (物件価格(税抜)×3%+6万円)+消費税 |
宅地建物取引業者の報酬規定が2024年7月1日に改正され、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。仲介手数料の上限引き上げにより、宅地・建物の物件が100万円でも300万円でも、物件価格が800万円の宅地建物の場合、売主は最大33万円の仲介手数料を受け取れるようになりました。
一方で、801万円以上の物件の仲介手数料は、従来通り、「(物件価格(税抜)×3%+6万円)+消費税」です。この速算式を仮に5,000万円の収益物件に当てはめると、仲介手数料の上限額は171.6万円になります。各不動産会社は、この上限額の範囲内で、仲介手数料を設定します。
銀行事務手数料
銀行事務手数料は、「定額型」と「定率型」の2種類があります。
- 定額型:10〜30万円などの定額であるタイプ
- 定率型:「借入額×3%」のように金額が決まるタイプ
銀行事務手数料の目安については、定額制の場合が3〜6万円ほど、定率制の場合が借入額の1〜3%が一般的です。
ただし、定額制を採用している金融機関では、借入額が大きくなると銀行事務手数料が10万円以上かかる場合もあります。一方、定率制でも、借入額が大きくなるほど、銀行事務手数料の金額も高くなります。
融資保証料
借主の信用度や支払期間によって異なりますが、融資保証料は借入額の1.1%が目安です。たとえば、4,000万円程度の収益物件であれば、銀行事務手数料と合わせて50万円程度を見込んでおきましょう。
ただし、融資保証料は支払い方法を工夫することで、支払総額を抑えることが可能です。具体的には、契約時に一括で支払う支払い方法である外枠方式で支払うと、融資の金利に年0.2%〜0.3%を上乗せして支払う内枠方式よりも支払総額を抑えられます。
登記費用(登録免許税・司法書士報酬)
登録免許税は、登録免許税法によって課税標準額が決まっています。課税標準額を計算する際の税率は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所有権保存登記(例:新築建物を購入するとき) | 0.4% |
| 所有権移転登記(例:土地を購入するとき、中古建物を購入するとき) | 2.0% |
| 抵当権設定登記(例:融資を受けるとき) | 0.4% |
土地や建物を購入する際にかかる登録免許税の金額は固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。
一方で、不動産投資ローンを組む際にかかる抵当権設定登記の登録免許税は、借入額に0.4%を掛けて計算します。
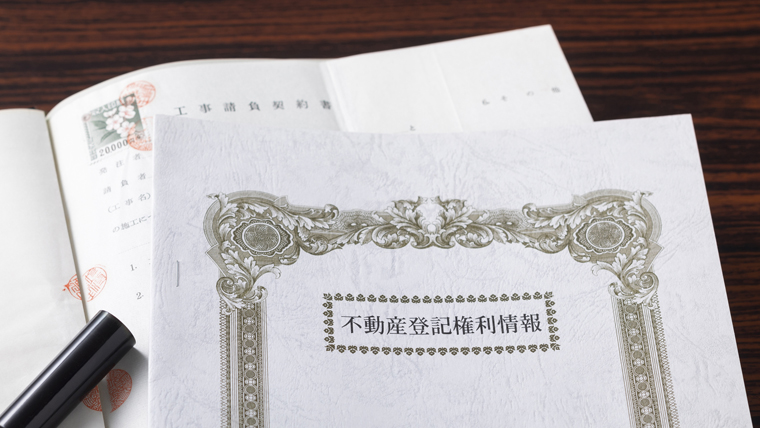
以上を踏まえると、仮に新築で収益物件を建てるとすると、最低でも3回は登録免許税が発生するというわけです。
他方、登記業務を担う司法書士に支払う報酬の金額は10〜20万円程度が目安です。
各種税金(不動産取得税・印紙税・固定資産税・都市計画税)
不動産取得税
不動産取得税は登録免許税と同様、「固定資産税評価額×税率」で決まります。2027年3月31日までに取得した不動産の税率は次のとおりです。
| 不動産の種類 | 税率 |
|---|---|
| 住宅 | 3% |
| 住宅以外の家屋 | 4% |
| 土地 | 3% |
ただし、宅地やそれと同じ扱いを受ける土地については、固定資産税評価額の2分の1が課税評価額になります。
不動産取得税が発生するタイミングは、収益物件を取得してから3〜6カ月後です。各都道府県から納税通知書が届くため、届いた後は期限までに税金を納めましょう。
印紙税
印紙税は、経済取引の規模によって税率が異なる累進課税制です。そのため、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書)に記載された金額に応じて税額が決まります。税額は次のとおりです。
| 契約金額 | 税率 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額に記載のないもの | 200円 |
不動産の売買契約書のうち、記載金額が10万円を超え、2027年3月31日までに作成したものは軽減税率が適用されます。ただし、金銭消費貸借契約書は軽減税率の対象外のため、注意しましょう。
また、印紙税の税率は印紙税法改正により変更になる場合もあります。国税庁のホームページで最新情報をチェックしたうえで、印紙を購入しましょう。
固定資産税・都市計画税
1月1日の時点で不動産を所有する人に課税される固定資産税と都市計画税の納税額の計算式は次のとおりです。
| 固定資産税 | 固定資産税評価額×1.4% |
|---|---|
| 都市計画税 | 固定資産税評価額×0.3% |
年の途中で売却・購入しても、その年の固定資産税と都市計画税は売主に全額課税されます。ただ、物件を買主に引き渡した後の税額を売主が支払うのは道理に合いません。そのため、物件の引き渡し時に、買主が納税額の日割りをした税額分を売主に支払い精算するのが一般的です。
火災保険料・地震保険料
火災保険料の保険料は収益物件の構造や築年数、面積によって変わりますが、区分ワンルームマンションの場合は1年間で約2万円です。壊れやすい木造の物件では、鉄筋コンクリート造の3倍ほどになります。
一方、火災保険の付帯として加入する地震保険料は政府と民間の保険会社が共同で運営する保険のため、保険会社による違いはありません。ただし、地域によって基本料率が違うため、事前に確認しておきましょう。2022年10月1日以降に地震保険に加入した場合の東京都の料率は、次のとおりです。
| 都道府県 | イ構造(主として鉄筋・コンクリート造建物等) | ロ構造(主として木造建物等*) |
|---|---|---|
| 東京都 | 27,500円 | 41,100円 |
*「耐火建築物」、「凖耐火建築物」および「省令凖耐火建物」などに該当する場合は「イ構造」になります。
ここからは、ワンルームマンション投資と一棟マンション投資にかかる初期費用をシミュレーションを通じて確認しましょう。
ただ、あくまでもシミュレーションであり、投資する物件によって変動する点にご留意ください。
ワンルームマンション投資のケース
〈シミュレーション条件〉
- 物件価格:3,000万円
- 新築ワンルームマンションを9月1日に購入
- 借入額:2520万円
- 固定資産税評価額:2,100万円(土地の評価額が1470万円、建物の評価額が630万円)
- 火災・地震保険加入:2万円
- 消費税率:10%
| 費用の種類 | 初期費用 |
|---|---|
| 物件の頭金 | 300万円 |
| 不動産仲介手数料 | 105.6万円 |
| 銀行事務手数料(定率制) | 50.4万円(借入額の2%) |
| 融資保証料 | 27.7万円(借入額の1.1%) |
| 登録免許税 | 約44.7万円 (所有権保存登記12.6万円、所有権移転登記約22万円、抵当権設定登記約10万円) |
| 司法書士報酬 | 10万円 |
| 不動産取得税 | 44.1万円 |
| 印紙税 | 2万円 |
| 固定資産税・都市計画税 | 9.8万円 (9〜12月の4カ月分の清算金) |
| 火災保険料・地震保険料 | 2万円 |
| 初期費用合計 | 約596.3万円(物件価格の約19.9%) |
一棟マンション投資のケース
〈シミュレーション条件〉
- 物件価格:1億円
- 中古の一棟マンション(築15年)を7月1日に購入
- 借入額:8400万円
- 固定資産税評価額:7,000万円(土地の評価額が4,550万円、建物の評価額が2,450万円)
- 火災・地震保険加入:10万円
- 消費税率:10%
| 費用の種類 | 初期費用 |
|---|---|
| 物件の頭金 | 1,000万円 |
| 不動産仲介手数料 | 373.26万円 |
| 銀行事務手数料(定率制) | 168万円(借入額の2%) |
| 融資保証料 | 92.4万円(借入額の1.1%) |
| 登録免許税 | 約150.9万円 (所有権保存登記49万円、所有権移転登記約68.3万円、抵当権設定登記約33.6万円) |
| 司法書士報酬 | 20万円 |
| 不動産取得税 | 約189万円 |
| 印紙税 | 6万円 |
| 固定資産税・都市計画税 | 49万円 (7〜12月分の6カ月分の清算金) |
| 火災保険料・地震保険料 | 10万円 |
| 初期費用合計 | 約2,058.6万(物件価格の約20.6%) |
不動産投資の初期費用を抑える方法には次の5つがあります。
- 仲介手数料を値下げ交渉する
- 頭金を減らす
- 資産価値の高い不動産を選ぶ
- 売主が不動産会社である収益物件を購入する
- 個人の属性の高さを利用して融資を活用する
不動産会社や収益物件によっては実践できない場合がありますが、ぜひ試してみてください。
仲介手数料を値下げ交渉する
仲介手数料は宅地建物取引業に基づいて上限額が決まっていますが、上限額は法定で支払う金額ではありません。交渉によって値下げしてもらえる可能性があります。
ただし、交渉の内容次第では、担当者のモチベーションを下げてしまう点に注意が必要です。そのため、値下げ交渉は、自己資金に余裕がないといった正当な理由がある場合に行いましょう。
頭金を減らす
属性が良い方や、すでに取引先銀行をお持ちの方は、頭金を減らせる可能性があります。
ただし、不動産投資ローンの頭金を減らすと、借入額が大きくなるため、月々のローン返済額と利息負担額が増えます。結果として、返済負担の増加によりキャッシュフローに関する問題に直面しやすくなる点に注意しましょう。
また、変動金利で借り入れしている場合、金利上昇に伴って利息負担額も大きくなる点にも留意が必要です。
資産価値の高い不動産を選ぶ
資産価値の高い収益物件は担保評価が高く、借入額を増やしやすいため、初期費用を抑えやすい傾向があります。資産価値の高い収益物件の特徴は次のとおりです。
- 利便性が良く、人気エリアに立地する物件
- 地価が安定しており、収益性が高い物件
- 物件品質が高く、長期間住める物件
資産価値が高い分、物件価格も高くなりますが、融資を利用すれば結果的に少ない自己資金で投資をスタートできるでしょう。
売主が不動産会社である収益物件を購入する
不動産会社が売主の場合、仲介手数料がかからないため、初期費用を大幅に削減できます。
ただし、仲介手数料がかからない取引では、売主側(不動産会社)に有利な内容の契約書が提示されたり、選択できる物件が限られたりするデメリットがあります。
また、売主物件は不動産会社が売買価格を決めるため、仲介物件と比べて割安になるとは限りません。そのため、収益物件を購入する際には、「物件価格+仲介手数料」で物件を比較し、総合的に判断することが重要です。
個人属性の高さを利用する
個人属性が高ければ、ローンの審査時に有利になるため、有利な条件で融資を受けられる可能性があります。有利な融資条件に直結し、審査時に評価されやすい個人の属性は次のとおりです。
- 年収800万円以上
- 医師や公務員、士業、上場企業社員などの職業についている
- 代表取締役をはじめ、高い地位
これらの属性に当てはまる場合は、有利な条件で融資を受けられ、少ない自己資金で不動産投資を始められるでしょう。
不動産投資の初期費用は物件によって異なりますが、目安としては物件価格の約16%です。あくまでも「約16%」は目安に過ぎませんが、初期費用の目安を理解しておくと、初期費用の多寡について判断できるようになります。
さらに、「頭金を減らす」「資産価値の高い不動産を選ぶ」といった初期費用を抑える方法を理解しておくと、必要な自己資金の削減が可能です。

今回ご紹介した方法以外にも、豊富な実績や金融機関へのネットワークがある不動産投資会社が扱う物件であれば、自己資金が少なくても好条件で融資を受けられる場合があります。それを踏まえ、不動産投資会社に一度相談してみるのがおすすめです。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F
【営業時間】9:30~18:30
【定休日】土・日・祝
キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.


